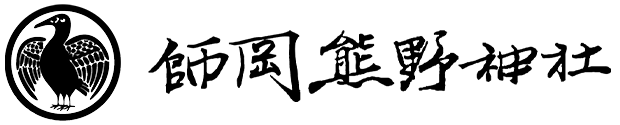熊野神社の歴史
神亀元年
全寿仙人が熊野山に来て、柳の木の洞窟で修行を始め、師岡熊野宮の基礎を築きました。数年後、牛王宝印を授かりました。
仁和元年
光孝天皇は六条中納言の藤原有房卿を勅使として師岡に派遣し、社殿を造営。また、社頭には「関東随一大霊験所熊埜宮」と書かれた勅額を賜りました。これ以降、宇多天皇、醍醐天皇、朱雀天皇、村上天皇の勅願所となりました。そして、熊埜神社の別当として、隣地に全寿院法華寺が建立されました。
天暦3年
村上天皇の時代のことです。1月7日に神託があり、1月14日の晩に氏子たちが集まって27本の筒と梛木の葉と米を混ぜて粥を作り、その粥を使って一年間の農作物の出来栄えとその年の吉凶を占う神事が行われることになりました。この神事は「筒粥神事」と呼ばれます。
承安4年
源義信の子である延朗が熊野宮に籠もっている時、全国で早魃が発生し、国内の山河の流れがすべて止まりました。高倉天皇は当社に勅使を派遣し、延朗に雨乞いを命じました。延朗はただちに龍頭を巡り、八大龍王を勧請しました。その結果、大雨が二日三夜続けて降り続きました。これに感謝して、大般若経六百巻を書写し、熊野宮に奉納しました。この神事は「雨乞神事」と呼ばれます。
元暦元年
1月8日、源頼朝は平家討伐の祈願を熊野宮の本殿で行いました。頼朝は怨敵退散と悪魔降伏を祈念し、大蛇を模した20尺のシメ縄を作り、それを東西南の村境に駆け巡らせました。これが師岡の「しめよりの神事」の始まりです。
観応2年
6月17日の夜半、雷火により社殿が焼失しました。しかし、神宝や神体などはすべて「の」の池に投入されていたため、無事でした。
貞治3年
熊野山縁起が完成しました。この5月に別当法華寺の住僧である瑞海が記したもので、現在も社宝として保存されています。
正德2年
師岡熊野神社の現在の本殿が建立されました。
昭和60年
11月24日、昭和天皇御在位60年記念事業の一環として熊野郷土博物館が開館されました。
平成元年
御大礼事業の一環として、以下の施設や設備が整備されました:
- 斎館の新築
- 境内の整備
- 石燈篭の建立
- 「い」の池の護岸工事
- 駐車場の整備
さらに、神社の鳥居脇に荘厳な石積みが奉納されました。
平成13年
内親王殿下誕生記念事業として稲荷神社周辺の整備を行いました。
平成18年
百二十年ぶりの氏子総勧進による「平成の大修造」が竣工しました。
- 本殿が修復され、覆殿・敷殿・翼殿が新築されました。
- 社務所が増築されました。
平成28年
「平成の大修造第二期」が完了しました。
- 手水舎が新築されました。
- 境内の神社が整備されました。
- 参集殿が改修されました。
令和元年
御大典記念事業として、社殿裏の整備が行われ、「令和神苑」が完成しました。
熊野郷土博物館について
当館は、昭和25年9月、終戦後の混乱の中、郷土史に深い関心を寄せていた先代宮司、石川武靖によって設立されました。
当神社の裏山(指定地域史跡)からは、縄文時代前期の遺物が数多く出土しており、この地には遠い原始時代から人々が居住していたことが明らかになっています。また、この地方は最近まで農村地帯であり、現在でも伝統が息づいていますが、都会化の進行に伴い、貴重な民族資料が消えつつあることも事実です。
さらに、当神社には、筒粥神事や土用丑の日の神事といった特別な神事が古くからそのままの形で伝えられており、これらの神事に関する各種の資料も保存されています。時代の移り変わりとともに貴重な郷土資料が失われていくことを憂慮した先代宮司は、収集した資料や神社の宝物、文書約二千点を公開し、現代の郷土史ブームの中で大きな役割を果たしました。
昭和60年11月、先代の精神を継ぎ、天皇陛下御在位六十年奉祝記念として当館を新築しました。これにより、更に多くの人々に郷土の貴重な資料を知ってもらい、神社への関心を深め、郷土愛の発揚に貢献することを願っています。
※神社施設改修工事の為、令和4年から当面の間、誠に恐縮ですが、博物館の入館は一時休止とさせて頂きます。
。